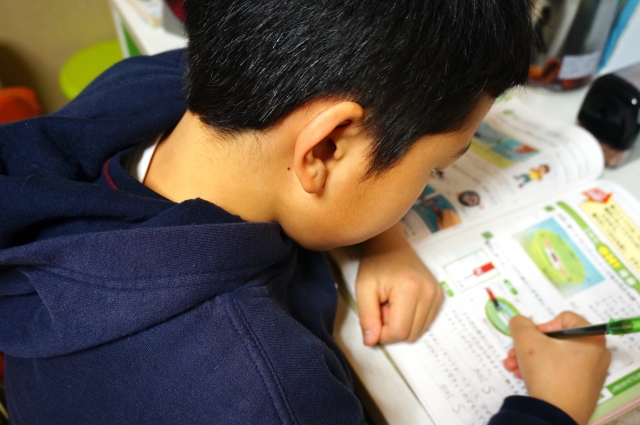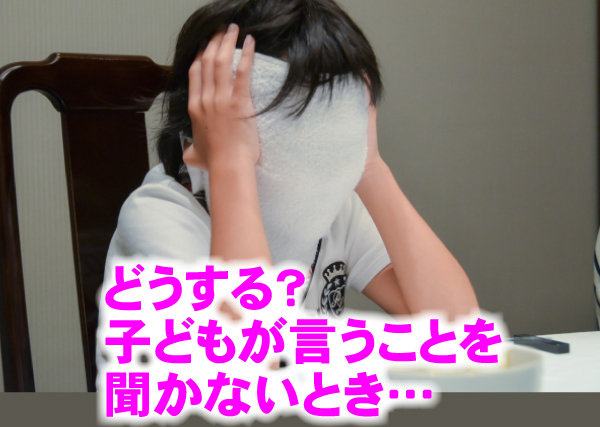
「子供が言うことを聞かない」
そんな声を子育て中の方から良く聞きます。
2才とか3才のイヤイヤ期も大変でしょうが、子供が小学校高学年とか中学生になって、親の言うことを聞かないのは本当に困ります。
私は長く教育界にいたので、そういった相談を受けたこともあったのですが、そんな時は「良かったですね!」とお返事していました。
すると皆さん最初は驚くのですが…
もちろん、その話には続きがあります。
目 次
子供が言うことを聞かない 中学生はどうすればいい?
まず、先ほどのお話の続きから…
なぜ、親の言うことを聞かないのが良かったのか?
それは、そのお子さんが正常な発達をしていることの証拠だから(^^)/
逆を考えてみればわかりやすいです。
お子さんが3才の時に
「〇〇ちゃん、おもちゃの後片付けして!」
『は~い、ママ!』
…素直でいいですよね!
お子さんが14才の時に
「〇〇くん、勉強して!!」
『ハイ、お母さん!』
…手がかからないでよさそうです!
お子さんが30才になった時に
「〇〇さん、△△さんと結婚して!」
『はい、わかりましたお母様!』
…想像してみてください。何だか気持ち悪くないですか?
もちろん、言うことの内容にもよりますが、30才や40才になってもまだ父親や母親の言うなりだったら大変です(^^;)
つまり、お子さんがあなたの言うなりにならなくなったということは、人として自立している証拠です。
「いやいや、言いなりになることを要求しているのではないのです。そういうことじゃなくて、ささいなことや何を言ってもダメなんです」
こう思われる方もいらっしゃるでしょう。
そんな場合は、父親や母親の言う内容や言い方によるかもしれません。
パパやママの言う内容に問題がある場合
もしかして、都合の良いところだけ言うことを聞かせようとしていないでしょうか?
「ちゃんと宿題をしなさい!」といちいち指示してみたり…
子どもが『〇〇高校に行きたい』と言った途端に
「あそこはダメ、△△高校にしたら?」と言ってみたり…
こんなふうに言うことの一貫性が無いと子どもでなくても、言ったことに素直に従いたくないと思うでしょう(^^;)
子供が言うことを聞かない原因は何?
ここまでお伝えした内容で何となく分かっていただけると思いますが、小学校高学年から中学生にかけての、いわゆる「思春期」「反抗期」の子どもが言うことを聞かない原因は大きく2つの理由があります。
①思春期特有の現象として反発する場合
この時期には、指示だけではなく他にも気をつけたいことがあります。
思春期になったら指示は控えましょう
「〇〇しなさい」
「勉強しなさい!」、「早く風呂に入りなさい!」、「早く寝なさい!」
これらはみんな「指示」です。
子どもが小学校高学年から中学生の頃になると、親の言う通りにやってきた子ども時代を卒業して、
自分で考え、自分で判断して、自分の力でする自立した人になろうとしています。
ただ、まだ自立していないのに、言うことだけ一人前というギャップはありますが(^^;)
中学生の子への批判や裁判には特に注意をしましょう
『ダメね、〇〇ちゃんは! 約束を直前で破るなんて最低!』
こんなふうに批判するのはあまり良くない対応です。
『それは先生の言うことが正しいわね、先輩の言うことは◇◇だからちょっと無理があるわ』
こんなふうに子どもの言う内容を元に親が判断してまるで裁判やジャッジのように正しい結論を導き出す必要もありません。
こんな時は共感したり、励ましをしてあげればいいんです。
『あら、ドタキャンは大変だったわね…』
『それは大変、あなたも困ったでしょうね』
良かれと思ったアドバイスなのに…
アドバイスや助言は一般的に良いことのように言われていますが、中学生には考えなしのアドバイスも禁物です。
思春期の頃の子どもには無用なアドバイスや助言もうっとうしくなることがあります。
考えてみると私たちは相手が大人の場合にむやみにアドバイスをしません。
旦那さんに
「仕事、今度からもっとこうした方がいいんじゃない?」
近所の人に
「子どもさんに対してそういう言い方は良くないと思いますよ、もっとこうした方が良いんじゃないですか?」
これではお節介おばさん、お節介おじさんになってしまいます(^^;)
もちろん、「どうしたらいいんでしょう?」と聞かれたときに適切なアドバイスをするのは大切です。
お子さんも同じこと、子どもから「どうしたらいいと思う?」と聞かれたときにアドバイスをすることで十分です。
②大人でも反発したくなる、言うことの内容の問題
恋人同士でのこんなやりとりはどうでしょう?
『何でもいいよ』
「じゃぁ、美味しい中華のお店があるからそこにしようか」
『中華はイヤ、今日はコッテリしたものを食べる気分じゃないから』
彼氏が「何だよ、何でもいいって言ったのに。そんな気分だったら最初から言ってくれれば良かったのに…」そう思っても無理はありません。
子どもも案外そう思っているのかもしれません(^^;)
・この前言ったことと違うなど言うことに一貫性がない
・子どものためと言いながら親の都合を押しつけてくる
こんな言う内容に注意したいものですね。
子供が言うことを聞かない場合の上手な対処法
先ほどの内容にそって上手な対処の仕方を考えてみましょう。
任せると言ったら任せる
『そんなこと聞いたって、どうせパパやママが決めるんでしょ』「ううん、今回は2泊だけど〇〇ちゃんの行きたいところにしようと思って…」
『ホント? じゃぁ韓国のバンタン食堂に行ってみたい』
「何よ、そのバンタン…って? だいたい海外はダメよ」
韓国なら1泊の弾丸旅行も可能です。
「わかった、パパもママも韓国のことをよく知らないから、〇〇ちゃんが中心になってプラン考えてくれる?」
『いいの? ヤッター! わかった、すぐ計画するね!』
「すぐパスポート作らなきゃね!」
任せると言ったら、とことん任せてみると子どもは変わりますよ(^^)/
そうは言っても任せられないこともありますよね、そんな時には聞かなきゃいいんです。
いつも言っていることと一貫性を持たせる
スーパーなどで見かけることがありますが…
子どもがお母さんにおやつをねだって駄々をこねたり泣きわめいたりした時に困った母親が
「今日だけだからね、今度からは絶対にダメだから…」
こう言われた子どもは心の中で思っています。
「今日が大丈夫なら今度からもOKだな!」って(^^;)
例外を作れば作るほど一貫性がなくなり、親の言うことへの信頼性がなくなっていきます。
いつもやさしいママが「ダメ」と言ったら絶対にダメなんだと、家にいるときにちゃんと体験している子は外出中でも親を困らせるようなねだり方をあまりしないはずですが(^^;)
「今日だけは…」は禁句ですね。
本当に子どものために言っているのだろうか自問してみる
「はやくお風呂に入りなさい」
「〇〇時には寝なさい」
子どもに言う言葉の多くは実は親の都合です(^^;)
「傘を持って行きなさい」
「宿題をちゃんとやりなさい」
これらは一見子どものために言っているようですが、親が勝手に「その方が良いから」と思っているだけかもしれません。
雨に濡れて困ることが何度か続けば天気予報を見て自分で考えるようになるかもしれません。
宿題を忘れて怒られて困ることが続けば自分からやるようになるかもしれません。
結局のところ、
・しないと自分が困る
そんな経験を重ねていくことで次第に大人へと自立していくのでしょうね。
中学生の子どもが自分がしたいと思うためには
・「昨日は遅くまで頑張っていたわね!」と自分からしたことを見逃さないで認める。
・子どもの興味関心のありそうなことや、我が子の優れている部分を見つけるように心がけ、その体験がしやすい環境を作る
こんなことを心がけてやると良いのではないでしょうか。
中学生の子どもが、しないと自分が困るようにしてあげるには
一番心がけたいのは、責任を子どもにとらせると言うこと。
言い方を変えると、子どもが自分のやったことの結果を自分で受けとめることができるようにしてあげたいですね。
例えば、幼い子どもが麦茶をコップに注ごうとしてこぼしたとします。
「ダメでしょ! 気をつけないと! いい? 今度からママが入れるから」
これではいつまでも結果を受けとめることができないので、ボトルからコップに上手に注ぐことにつながりません。
「今日は上手に出来なかったね」と言って、さらに…
「こぼしてしまったときは、ここにある布巾で拭いてテーブルをきれいにしてほしいんだけどできるかな?」と後片付けの方法を教えれば、何度でもチャレンジしてきっと上手になります。
何よりも、自分のやったことの結果を自分で受けとめる、つまり責任をとることを学べる価値は大きいです。
これを中学生とのやりとりで応用するように心がけたいですね(^^)/
子供が言うことを聞かない 中学生の原因と上手な対処法のまとめ
子どもが言うことを聞かないときは次の点をチェックしてみましょう。
✔ 今までに言ったことと違うことを言ってはいないだろうか
✔ 子どものためと思っていたけど、本当にそうだろうか? 親の都合になっていないだろうか?
これらがだいたいOKであれば問題なし!
それでも親の言うことに何かと反発しているなら、それは思春期特有の自立の過程だと思って温かく見守りましょう。
この時期のお子さんへ接するときのコツは
✔ 指示や命令は控える
✔ 子どもの言ってきたことにいちいち判断したり、ジャッジ、や裁判をしない
✔ 過剰なアドバイスを控え、子どもから相談が来たときにはていねいな助言をする
あなたの旦那さまや奥様が言いなりにならないように、大人だって言うことは基本聞かないものですから(^^;)
それではまた!